生前対策はどのような種類がある?注意点やポイントを司法書士が解説!遺言・贈与・後見・家族信託・保険
人生百年時代と言われる現代で、老後の資金については非常に不安を感じる方も多いと思います。
健康寿命も延びる現在、自分らしい老後を送るために、また次の世代に財産を承継していくためには生前対策というのは欠かせないものだと思います。
生前対策とはいったいどのような事でしょうか。
その意味は人によって千差万別とも言えます。ある人には経済的な利益であったり、またある人には手続きの合理性の追求であったり、またある人には節税の対策が最優先だったりもします。
しかし、最も大切なことは自分の人生を主体的に捉え、そして安心して老後を過ごすための準備なのではないでしょうか。
司法書士として私たちがお手伝いできるようにするには、次のような項目を検討して、準備を進めるお手伝いができればと思っています。
生前対策を始める理由としては、次のようなきっかけがあります。
まず生前対策を行うことで、自分の人生について整理を行うことができます。
ある方は自分の財産状況に第三者の視点を入れることで、老後の過ごし方について新たな視野が開けることもあります。
例えば、相続の対策をしながら、先々こんな施設だったら入ってもいいな、というような施設選びのご検討を始める方もいます。
またある方は逆に、介護施設の入居を検討せざるを得ない状況になって初めて、自分の老後の財産の状況の検討や財産承継の方針、さらに自分の最後の姿をどのように迎えたいかなどを考え始める方もいます。
その多くが残された子どもや親族に迷惑を掛けたくない、という思いが共通しているように思います。
また、あまり考えたくないことになるかもしれませんが、相続人が多い方などにとっては、相続人の間での争いを防ぐ対策を行うということも、一つの生前対策と言えるでしょう。
生前対策をすることで得られるこれらのメリットというのは、自分らしく生きること、また家族の間のコミュニケーションを深めることにもなると思います。
生前対策には様々な種類があるため、以下では、生前贈与・遺言書・家族信託・任意後見制度・生命保険について司法書士目線で詳しく説明をしていきたいと思います。
生前贈与のポイントと注意点

まず皆さんが真っ先に思いつくのは生前贈与だと思います。
これは自分の意思がはっきりしているうちに、元気なうちに資産を家族に贈与することで、相続税の対策にもなりますし、確実にに次の世代、子どもや孫への資産を承継することができます。
これは教育資金に充てるため、金融機関等との一定の契約に基いて受贈者(財産を貰う人)の直系尊属(父母や祖母や祖父)から、贈与により取得した金銭を銀行等を通じて受けた場合など、(教育資金口座の開設)は、1,500万円までは、教育資金非課税申告書の提出等をすることにより、贈与税が非課税となります制度もあります。
特に教育資金贈与の制度などは税制面での優遇が強いので、お子様お孫様がまだ中高生の方は検討してみてはいかがでしょうか。
No.4510 直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁
また多くの方がご存知なのは、毎年、非課税の範囲内で行う贈与かと思います。
これは暦年贈与とおって、毎年、非課税の範囲内、または非課税の範囲を少し超える範囲で贈与をしていくことです。
ただこうした生前贈与については、金銭で行うのが通常で、不動産についてはなかなか行うのが難しいと言えるでしょう。
不動産で贈与を行う場合は登記をしなければいけませんし、年間100万や200万ぐらいの単位ですと、不動産については一度に全てを贈与することができず、何年もかけて毎年毎年コツコツと贈与の登記をしていく必要があります。
どうしても贈与の度に、・不動産の登録免許税 ・不動産取得税 といったような税金や、司法書士などの費用もかかってくるので、思ったよりうまく効果を得にくいのが不動産の生前贈与と言えます。
遺言書のポイントと注意点

2番目に検討されるのが、やはり遺言書です。
遺言書を作成することで、自分が亡くなった後の遺産の相続についての希望を明確にできます。
これにより、様々な相続に起因する関するトラブルを避ける手段にもなるでしょう。
遺言書の最も効果的なところは、やはり生前贈与と違い、「相続」を原因としてお持ちの財産を移せるところです。一般論として、相続の方が贈与よりも税金上でのメリットは大きいです。
考えてみれば当たり前のことで、相続より贈与の方が安く移せるのでしたら、みんな生前の贈与を選択してしまうでしょう。こうしたことが遺言の優れるメリットの一つと言えます。
ただ遺言書については、やはり「遺言書を書く」ということに対して心理的、手続き的なハードルを設けている方も多いのも事実です。
また相談の現場でよく言われるのが、『私は財産が少ないから』『うちの家族は仲がいいから、相続人が揉めないから』などとおっしゃる方も非常に多いです。
多くの相続の現場を見てきた身としては、特に財産の少ない方にとっても遺言は大きなメリットはあると言えます。財産が少なくとも、適応する法律が変わることもなく、また相続にかかる手続きが変わる訳ではありません。
財産が少ないにもかかわらず相続人が多い場合、遺言がないと非常に相続に関する手間がかかり、相続財産額の割には手続きのコストが高くついてしまうことも多くみられます。
このため、自分の財産の後始末と言ってはなんですけれども、むしろ財産の少ない方ほど遺言書を書いておくことで、相続にかかるコストを削減するというのも、遺言を書く一つのメリットだと言えます。
もう一つ、遺言書を書くメリットが大きいのは不動産についてです。
不動産はどうしても分けることができないものです。また家族が居住する自宅などは、売ることも難しいでしょうから、より分けることが困難といえます。
例えば、二世帯住宅で子どものうちと一人と暮らしているようなケースでは、やはり同居する子に確実に不動産を相続させてあげたいというものが親心ではないでしょうか。
こういうケースでは、揉め事が起こるかどうかは、実際にご自身である張本人が亡くなった時にしかわかりません。
仮に仲が良いからと思っていて遺言書かなかった場合、死後に万が一トラブルになってしまった際は、当然ながらご本人は亡くなられているので、今更遺言の作成をやり直すことができません。
私は司法書士として、こうした場面に何度も立ち会ってきました。このため、保険という意味で、不動産だけ遺言を残しておく、というのも非常にメリットがあると思います。
家族信託のポイントと注意点
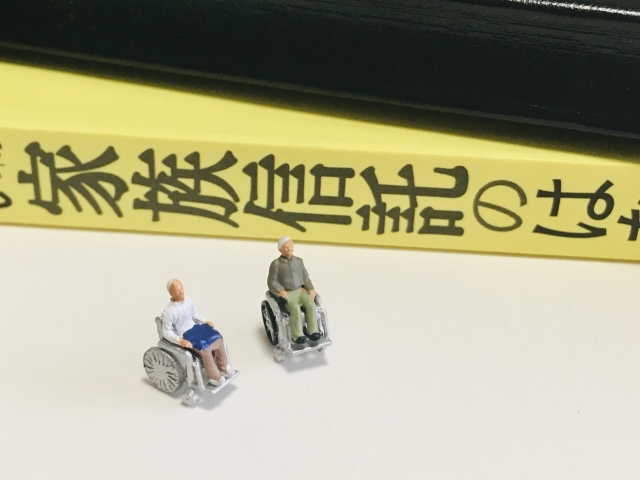
3つ目が家族信託です。
これは最近多く用いられる方法ですので耳にしたことのある方も多いのではないでしょうか。
家族信託というのは、ご自身の財産を生前に信託することで、その管理や処分の権限を親族に予め移しておくこと、仮に本人が認知症になったとしても、財産の管理処分などをスムーズにできるようにする方法です。
実際に、家族信託の多くが司法書士によって行われていると言われています。
これは家族信託が、非常に不動産と相性が良い制度からだからでしょう。
なぜなら不動産には登記簿謄本があり、不動産が信託が入ったこと、つまり信託財産である旨が登記をされます。
これによって、取引を行う第三者にとっても誰が不動産の管理者、信託でいえば受託者であるかが明らかですので、売買などの取引も安全に行うことができます。
不動産登記制度が発展した日本であるからこそ、非常に家族信託というのは、非常に有用な財産管理方法と言えるでしょう。実際に私の事務所でも、多くの家族信託の案件を手がけています。
また、もう一つのメリットとして、家族信託を遺言の代用として使うというケースも多く見られます。家族信託が終了するときというのは、不動産の観点からみれば原因は主に二つです。
1つは何らかの理由で管理者、つまり受託者が信託された不動産を売買するケースです。
ただ、これは売買で得た対価が現金に変わり、この現金については、引き続き信託が続きます。
このため厳密的には終了ではありませんが、不動産の登記簿上では信託が終了することになります。
仮にこうした信託不動産の売買を生前に行わなかったとして、信託が終了するケースともあります。
これは多くが預けた人、委託者が亡くなってしまったケースです。専門家が作る信託では通常、信託が終了する場合についても信託財産の帰属先について記載がされています。
今回のように委託者がなくなってしまったようなケースでは、多くは信託終了後の権利帰属先として受託者であったり、その不動産を継いでほしい人を記載することが非常に多いです。
これにより信託をされた財産においては、家族信託は実質的に遺言の代用のような役割を家族信託は果たしています。
認知症の対策にもなりますし、遺言の代わりにもなる。
こうした面で非常に家族信託使い勝手が良いため、多くの方に用いられていると言えるのではないでしょうか。
任意後見制度のポイントと注意点

4つ目が任意後見制度です。
任意後見と成年後見の違いについては、良く相談者様から尋ねられる点です。
大まかに言ってしまえば、任意後見というのは、自分の認知能力がまだはっきりしているうちに、もし自分が認知症になってしまった際には、誰に後見人になってほしいか、予め公正証書を通じて契約をしていく制度です。
これは私の事務所でも多くの方と任意後見契約をさせて頂いています。
というのも、他人である方の財産を預かるという点では、任意後見の制度というのは非常に有益な手段だからです。
公正証書において預ける側の意思を詳らかにし、いざ認知症となれば裁判所、さらには後見監督人による監視があることにより、金融機関においても非常に信用されている制度です。
また家族の中でも家族同士でも、この任意後見制度というのは多く用いられています。
認知症になってしまうと、当然本人には判断能力がないわけですから、自分の財産を管理してほしい人を自分で選ぶことはできません。
このため、まだはっきりしているうちに信頼できる人を親族の中から指定しておくというのは、非常に有益な選択肢ではないでしょうか。
一方で任意後見のデメリットとしては、どうしても専門家が後見人として指定されている場合でも、後見監督人といって、家庭裁判所の以外にも任意後見人を監督するものがつくこと、この点の費用面のデメリットがあるかもしれません。
しかし、自分の選んだ人を確実に後見人に指定できるという点での大きなメリットは、やはり代えがたいものがあるのではないでしょうか。
公正証書で作らなくてはいけないというハードルの高さもありますが、最近は非常に多く用いられている制度の一つですので、検討する価値があると言えます。
生命保険のポイントと注意点

5つ目に挙げられるのが、生命保険を使った対策です。
生命保険はご存知の通り、亡くなった際に、保険契約で指定した方に約束した金額を渡すという手段です。
保険金の受取人に相続人を指定することで、一定額、具体的には法定相続人の数かける500万円を上限として、非課税で次の世代に指定した金額を残すことができます。
これは相続税対策の初歩の初歩といってもいいでしょう。
司法書士として様々な方の相続を見ていますが、このはじめの一歩といえる生命保険の対策もしていない方が多いのも事実です。
正直なことを言ってしまえば、相続財産が概ね1億以下の相続では、例えば法定相続人が3人いれば1500万は生命保険金によって非課税で次の世代に承継できるので、こうした制度を使っているか使ってないかでかなりの差が出てきます。
不動産が多く、それに比すると金融資産の少ない方の場合、不動産を売却して現金化することによって保険に組み替えるというケースもよく見られます。
ご相談者様で80歳などを超えてくると、私は保険に入れないとおっしゃられるお客様も多くいらっしゃいます。
しかし、外資系の保険会社を中心に一時払いの終身保険、つまり保険金を一括して一括で先に払ってしまい、亡くなった際に相続人に保険金を支払うような保険というのも非常に多くあります。
こうした制度を使うことで、相続税の非課税枠というメリットも得つつ、自分が希望する人に相続財産を引き渡すということが可能になります。
一方で、生命対策、生前対策においても、失敗例などもよく見られます。
よく見られるるのが、自筆で書いた遺言書が要件を満たしていなかったり、またそもそも自筆の遺言書が発見されなかったり、また悪意を持った相続人に破棄をされたりなどというケースです。
自筆の遺言書というのは、専門家の目を介していないことが多いです。
このため皆さんの思っている以上に不備があることが非常に多くあります。
また、不備がなかったとしても、遺言書の中で指定されていない財産があったり、また遺言で指定した方が先に亡くなってしまったりすると、その部分の遺言というのが使えなくなってしまうこともあります。
いわゆる遺言における財産の漏れ、予備的事項の不記載とされる部分です。
繰り返しになりますが遺言書を用いる局面では、当然ながら書いた本人はこの世にいないわけですから、やり直しがききません。
やはりこうしたこともありますので、遺言書を書く場合は、専門家への相談をお勧めします。特に遺言書において、不動産に関係する分野でよく見られる失敗は、持分の一指定道路を書いていなかったり、不動産の物件漏れがあることです。
また、不動産について登記簿謄本の地番ではなく、住居表示で記載をしてしまっていることもあります。
住居表示でも自宅などの場合は法務局が登記を受け付けてくれる場合もありますが、地番と一致しないため却下されてしまうケースもこれまで見てきました。
理想的な生前対策の進め方
生前対策を始めるのは難しいと戸惑いの方もいると思いますが、相続に詳しい専門家のサポートを受け人の力を借りうると、思った以上にスムーズに進められることもあると思います。
また、自分自身の状況というのは、思っている以上に自分では把握できていないことも多いかと思います。
第三者の視点を入れることで、またアドバイスを受けることで、自分では気づかなかったような発見もあることも多くあると思います。
生前対策は、自分の未来を見据えた大切な準備です。
家族や相続人への思いやりを持って、自分の意思を形にすることで、より良い未来を築いていけるのではないでしょうか。
これをご覧になられた方というのは、まだ自分自身でご自身のことを決められる能力のある方だと思います。全く遅くありませんので、少しずつ前に進むことで、より良い人生や安心感を得られると良いと思います。
私たちの事務所でも、そうした方のお手伝いをできればと思っています。
当事務所では横浜市を中心として神奈川県全域から相続・生前対策のご相談をいただいております。
生前対策を検討する前にまずは経験豊富な司法書士に相談してみたいという方や、現状生前対策を考えているが、より良い方法がないか知りたいという方からのご相談も多々お受けしておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
当事務所の無料相談はコチラからご確認ください。
- 【不動産の生前対策マニュアル】相続税対策のポイントやリバースモーゲージなどのメリット・デメリット比較
- 家族信託を検討した方がいいケースとは?場合によっては実施しない方が良いの…?
- 共有問題や認知症問題を解決するための家族信託
- 「実家を○○に継がせたい」60~80代の方向け遺言書で指定する不動産相続の成功事例・失敗例と注意点
- 資産管理法人×家族信託の連携!賃貸アパートや資産管理法人における相続の「ハイブリッド戦略」
- 不動産相続の相続税の悩みを解消! 生命保険で叶える「納税資金」と「公平な遺産分割」
- 後見制度(任意後見と法定後見)の前にできることはないの?
- 自筆証書遺言のよくあるミス、無効にならないための注意点とポイント
- 夫婦間贈与の特例とは?適応条件や注意点を司法書士が解説!
- 【相続・生前対策】遺言の重要性と書かなかった失敗を事例をもとに司法書士が解説!
- 【認知症】実家の父の様子がおかしい?資産家の財産を守る家族信託
-
相談事例2026/02/19
-
お知らせ2026/02/12
-
相談事例2026/02/04
-
お知らせ2026/01/29
-
相談事例2025/11/24
-
相談事例2025/09/14
-
お知らせ2025/07/22
-
相談事例2025/07/14
-
お知らせ2025/07/08
-
お知らせ2025/07/07







