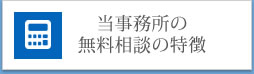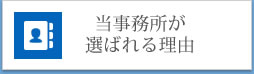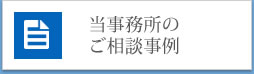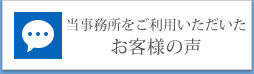モーリー・ロバートソン氏の相続から考える国際相続の注意点を司法書士が解説
2026(令和8)年1月29日、国際ジャーナリストとして活躍されているモーリー・ロバートソン氏が63歳で急逝されました。
日米両国にルーツを持ち、東大とハーバードで学んだ知性、そして鋭いコメンテーターとしての顔。
彼の突然の訃報は、日本社会に大きな衝撃を与えました。
一方でこうした著名な「外国籍」の方の訃報に接した際、私たち実務家(司法書士)が真っ先に考えるのは、残されたご親族が直面するであろう「国際相続」の複雑さです。
もしあなたや、あなたの周りに、外国籍の方や海外に資産を持つ方がいれば、今回のケースは決して他人事ではありません。
また横浜では中国や台湾、韓国などにルーツを持つ方の相続登記や生前対策にあたる機会も大変に多くあります。
国際・渉外相続専門とする司法書士の視点から、モーリー氏のケースを例に、外国籍の方の相続における大きな壁を解説します。
Contents
最初の壁:どこの国の法律が適用されるのか?(準拠法の問題)
まず専門家が最初に考えるのが「反致」の問題です。
日本の法律(法の適用に関する通則法第36条)では、「相続は、被相続人の本国法(国籍のある国の法律)による」と定められています。
亡くなられたモーリー氏は米国籍でした。
この場合原則として「アメリカの法律」に従って相続が進められることになります。しかし、ここからが「国際相続」の難解なポイントです。
「反致(はんち)」という法的な問題
アメリカは日本と異なり、財産の種類よって適用する法律を変える「相続分割主義」を採っています。
・動産(現金・預金・株式など):亡くなった時の「住所地」の法律に従う
・不動産(土地・建物):その「不動産がある場所」の法律に従う
モーリー氏は長年日本を拠点に活動されていました。
もしモーリー氏が日本に自宅不動産を持っていた場合、アメリカ法は「不動産については所在地である日本の法律に従ってね」と指定します。
すると、日本の法律が再び呼び戻される「反致」が起こり、結果として日本の民法が適用されることになります。
第二の壁:戸籍がないため「誰が相続人か」をどう証明するか
日本国籍の方が被相続人の場合、役所で「戸籍謄本」を取れば誰が相続人であるか書面で疎明できます。
しかし、こうした戸籍の制度自体が世界的にみると寧ろイレギュラーな制度です。
中国や韓国に似たような制度がありますが、日本ほど人の一生分をカバーするような詳細なものではありません。
韓国には、「家族関係登録簿」と呼ばれる制度がありますが、これも家族関係、婚姻関係、入養、親養子入養などを示すもので、2008年に従来の戸籍制度から新たに創設されたものになります。
中国には「居民戸口簿」とよばれる制度がありますが、これは身分証明よりも居住実態を管理する「住民票」に近い性質を持っています。
また、そもそもアメリカなど欧米各国には、戸籍制度やそれに類似した概念がありません。
宣誓供述書(Affidavit)の作成
モーリー氏のように米国籍の方が亡くなった場合、かつ相続人にも外国籍の方がいるような場合、司法書士が相続登記(名義変更)を行うためには、戸籍の代わりに以下のような膨大な書類を精査・準備する必要があります。
・出生証明書・婚姻証明書・死亡証明書(米国の各州発行)
・宣誓供述書(Affidavit):相続人本人が「私たちが唯一の相続人です」と公証人の前で宣言し、認証を受けた書類です
これらの書類は当然すべて英語などの外国語です。
日本の法務局などで不動産登記をとして提出するには、これら全てに日本語訳を付けなければなりません。(※昭和30年7月4日 民事甲第1412号回答「登記申請書に添付する委任状その他の附属書類が外国語で作成されているときは、その翻訳文を付綴し、翻訳者がこれに署名捺印すべきである。」)
パートナーシップの法的壁
報道によれば、モーリー氏には20年来のパートナーである俳優の方がいらっしゃいました。
しかし、日本の現行法(民法)では、法律上の婚姻関係になければ「配偶者」としての相続権は認められません。
もし遺言書がなかった場合、日本にある不動産の相続権は、日本の民法が適用される限りにおいて、パートナーよりも血縁者が優先される可能性があります。
第三の壁:「印鑑証明」が通用しない世界の戦い
また日本で不動産を売却したり名義を変えたりする場合、必ず「実印」と「印鑑証明書」を求められます。
これは遺産分割協議書において捺印を要する場合も同様です。
しかし、海外居住者や外国籍の方に「印鑑証明を出してください」と言っても、そんな制度自体が存在しません。
これは印鑑証明書の制度自体が、日本における住民登録制度・住民票に紐づいているためです。
サイン証明(署名証明)の取得
日本に住所を有さない方が相続人になる場合、印鑑証明の代わりに、本人が領事館や公証人など、公務員やそれに準じる者の前でサインをし、これは本人の署名に間違いありませんという証明をもらう必要があります。
これは署名証明書(サイン証明)や宣誓供述書(Affidavit)と呼ばれるものです。
ただこの認証を受ける相手というのは、基本的に認証を受ける人の「国籍」に属する公務員である必要があります。
このため、日本に住む外国籍の方が、「日本の公証役場」で認証を受けたとしても、ほぼ意味のない書類であります。
この認証を受ける手続きが、かなり大変で手間のかかる手続きとなります。
経営者・資産家への警鐘:遺言こそが「唯一の地図」
モーリー氏のような国際的な活動をされていた方は、日本だけでなく海外にも銀行口座や資産を持っていた可能性があります。
もし事前の対策をしていなければ、残された家族は「プロベート(遺産管理手続)」という、数年単位の時間と多額の弁護士費用がかかる英米法特有の裁判手続きに巻き込まれることになります。
これを回避する唯一といってもいい手段が、「遺言書」です。
そもそも外国籍の方が、日本の公証人において、日本の法律(民法)に則り、遺言書を書いて有効なのでしょうか。
これは先ほどの認証を受けるためにはその人の「国籍」に属する公務員でなければならない、とする先例と矛盾するように感じますが、こちらは有効な遺言書となります。
直接的な法的根拠は、「遺言の方式の準拠法に関する法律(通称:遺言方式準拠法)」です。
遺言の方式の準拠法に関する法律第2条 第1号
「遺言は、その方式が次に掲げる法のいずれかに適合するときは、方式に関し有効とする。 行為地法(遺言をした場所の法律)」
この法律により遺言者がどこの国の人間であっても、「日本という場所で、日本の法律が定めるやり方(公正証書遺言など)」で遺言を作成すれば、その形式は法的に有効であると認められます。
原則として、モーリーさんのような米国籍の方であれば、遺言の「内容」が有効かどうかは「アメリカ法」で判断されます。
しかし、ここが実務上のポイントですが、多くの国には「遺言者が、特定の財産についてはその場所の法律(日本法)を適用してほしいと選んだ場合は、それを認める」というルール(反致や指定)があるため、日本の公証人が日本法に則って作成した内容も、実質的に有効となるケースがほとんどです。
特に外国籍の方や、国際結婚をされている方、海外に資産がある方は、以下の2点を今すぐ検討すべきです。
・各国の方式に合わせた遺言の作成(日本用と海外用、あるいは国際遺言)
・準拠法の指定(どの国の法律で相続させてほしいかを明記する)
実務的なメリットが極めて大きいため、司法書士としては日本に住んでいらっしゃる外国籍の方には、「日本の公証役場」公正証書を勧めて、実際に多くの方が遺言を作成していらっしゃいます。
これはやはり公的証明力の確保できる点が大きく「本国法による方式」で書かれた外国語の遺言を日本で執行するには、裁判所の検認や膨大な立証が必要になりますが、日本の公正証書ならそのまま日本の法務局や銀行で受理されます。
こうしたことから外国籍の方こそ、自筆ではなく日本の公証役場で作る「公正証書遺言」を強くお勧めします。
・公証人が本人確認を行うため、偽造の疑いを排除できる。
・原本が公証役場に保管されるため、紛失や隠匿のリスクがない。
・日本語で作成されるため、日本国内の不動産登記や銀行解約がそのままスムーズに進む。
おわりに
モーリー・ロバートソン氏が遺した数々の知的な言葉は、これからも私たちの心に残り続けるでしょう。
しかし、彼のような「境界を越えて生きた人」の相続は、残された人にとって、国境という高い壁を越える過酷な作業になりがちです。
「うちは家族仲が良いから大丈夫」 「日本に住んでいるから日本のルールでいけるはず」その思い込みが、国際相続では最大の足かせになります。
国境を越えて活動することは、素晴らしいことです。
ただ相続の場面では、その「国境」が壁になります。家族仲が良いことと、手続きが簡単であることは、残念ながら別の話です。
一度、ご自身の国籍、資産の所在、家族関係を整理してみる。それだけでも準備になります。
当事務所では、外国籍の方や海外資産が絡む相続登記・生前対策の無料相談を実施しています。
あなたの「万が一」が、家族の「途方に暮れる日々」にならないよう、一緒に準備を始めませんか。
当事務所では横浜市を中心に神奈川県全域から多数の相続のご相談をいただいております。
国際相続についても経験豊富な司法書士が親身に対応いたします。
少しでもご不安やご不明点があればお気軽に無料相談をご利用ください。
相談事例の最新記事
- 所有不動産記録証明制度の開始!「親の土地、どこにあるか分からない問題」がついに解決!?
- 相続放棄すれば実家の管理責任も消える?“負動産問題”の真実と、相続放棄後も残るリスクを司法書士が徹底解説
- 認知症対策になぜ家族信託が必要か/相続の失敗事例から学ぶ家族信託の必要性
- 不動産を「寄付」で遺すという選択肢~遺贈寄付の方法と注意点、司法書士による生前対策の重要性~
- 【遠野なぎ子さんの孤独死から考える】一人暮らし高齢者のリスクと、司法書士・不動産業者が支える「相続手続き」の役割
- ミスタープロ野球こと長嶋茂雄さんの相続から学ぶ生前対策の重要性を司法書士が解説
- 【複雑な相続】警察から疎遠な兄が亡くなった知らせが来た事例を司法書士が解説!
- 【兄弟間の相続放棄】複雑な相続放棄を実際にあった事例をもとに注意点やポイントを解説!
- 【相続】甥姪で相続不動産を共有名義にしてしまう注意点を司法書士が事例で解説
- 【相続・生前対策】先妻との子供がいるが、後妻(今の妻)の子供に財産を残す方法を事例で紹介
- 【相続事例】疎遠だった父が亡くなり病院から連絡がきたが再婚していて腹違いの兄弟がいたケース
- 兄弟相続の際は甥姪が相続人に?行方不明の場合はどうする?司法書士が解説
- 【相続事例】海外に嫁いだ姉の失踪宣告をして相続手続きを進めたケース
- <コラム> デジタル遺産 ~税務署は把握していたアプリの中の相続財産~(後編)
- 出張無料相談会のお知らせ
- 年末年始の休暇のお知らせ
- 【相続のQ&A】亡くなった父に遺言書があったが遺産分割をやり直すことは可能でしょうか?
- こんな時どうする?相続人不存在となった親族所有の不動産を買戻したいケース
- 【相続のQ&A】特別縁故者として認められるのはどのような人ですか?
- オンラインセミナーの開催について
- 【相続のQ&A】特別縁故者として相続財産を受領できるのはどのような関係の人ですか?
- 弊所代表の連載掲載のお知らせ
- 【相続Q&A】特別縁故者として被相続人の不動産を取得するにはどんな手続きが必要ですか?
- 【相続のQ&A】特別縁故者の申立てをすれば相続人でなくとも相続財産の受領は可能ですか?
- 【相続のQ&A】相続人不在の場合、従兄弟が相続できますか?相続財産清算人とは何ですか?
- 【相続のQ&A】相続人不在の場合、相続財産は自動的に国のもの(国庫帰属)になるの?
- 【相続のQ&A】法定後見制度と任意後見制度の違いについて教えてください②
- 【相続のQ&A】法定後見制度と任意後見制度の違いについて教えてください①
- 相談例100 遺留分の放棄と相続放棄の違いについて教えてください
- 【知らなきゃ損する!?】相続登記をやり直すと税金が課税される?司法書士が解説
- 相談例98 一度登記した相続登記をやり直したい
- 夏季休暇のお知らせ
- 相談例97 相続した不要な農地を処分したいです
- 相談例96 (登記と税金)③ 要らない土地を国に引き取ってもらう制度(相続土地国庫帰属制度)を使いたいです!
- 相談例95 (登記と税金)② マンションの相続登記で必要な税金(登録免許税)を教えてください
- 相談例94 (登記と税金)① 相続登記で非課税になるものを教えてください
- 弊所代表の連載掲載のお知らせ
- <相続に関する時事ニュース> 「一時」成年後見人制度の創設か?
- 相談例93 (相続全般)⑦ 相続人の中に認知症の者がいます
- 【司法書士が解説】相続人の中に未成年者がいる場合の手続きの進め方や注意点は?
- <相続に関する時事ニュース> 相続での不動産登記が義務化
- 相談例91 (相続全般)⑤ 夫婦間の贈与に関する特例2
- 相談例90 (相続全般)④ 夫婦間の贈与に関する特例
- <相続に関する時事ニュース> 路線価か、実勢価格か
- 相談例89 (相続全般)③ 農工銀行という銀行の抵当権の抹消
- 相談例88 (相続全般)②相続した不動産に抵当権が設定されたままです
- 相談例87 (相続全般)①相続放棄したい不動産の遺品整理
- 相談例86 (渉外相続)⑦外国籍の方の相続手続きを楽にする方法はないの?
- 相談例85 (渉外相続)⑥在日台湾人名義の父の不動産の相続
- 弊所代表の連載掲載のお知らせ
- 相談例84 (渉外相続)⑤在日中国人名義の父の不動産の相続
- 相談例83 (渉外相続)④在日韓国人名義の父の不動産の相続
- 相談例82 (渉外相続)③外国籍の夫名義の不動産を「相続」したい
- 相談例81 (渉外相続)②外国籍の夫名義の不動産を「処分」したい
- 相談例80 (渉外相続)①半世紀会っていない外国人配偶者からの遺留分請求は有効ですか?
- 相談例79 (相続/不動産)⑰相続した地方の不動産の解体を求められています。
- 相談例78 (相続/不動産登記)⑯従兄弟が死亡しましたが、相続人がいません。
- 相談例77 (相続/不動産登記)⑮父が、遺言書で不動産の遺贈を受けましたが・・
- 相談例76 (相続/不動産登記)⑭遺言書で不動産の遺贈(寄付)を命じられました(相続人が1人もいないケース)
- 相談例75 (相続/不動産登記)⑬遺言書で不動産の遺贈(寄付)を命じられました
- 相談例74 (相続/不動産登記)⑫遺贈の登記をしたいのに権利証が見つかりません
- 相談例73 (相続/不動産登記⑪)相続でも不動産取得税は課税されるの?
- 相談例72 (相続/不動産登記)⑩遺贈の登記ってどうやってやるのですか?
- 相談例71 (相続/不動産登記)⑨法定相続人への「遺贈」登記
- 相談例70 (相続と年金)④内縁関係でも年金はもらえるのですか?
- 相談例69 (相続と年金)③相続後に年金で何か貰えるものはありますか?
- 相談例68 (相続と年金)②年金は相続財産なの?相続税はかかるの?
- 弊所代表の連載掲載のお知らせ
- 相談例67 (相続と年金)①離婚した元夫が死亡しました
- 相談例66 (相続放棄)⑤相続放棄をした場合、遺族年金や未支給年金は受け取っていいの?
- 相談例65 (相続放棄)④相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
- 相談例64 (相続放棄)③日本国籍を離脱した相続人も相続放棄が必要?
- 相談例63 (相続放棄)②親が相続放棄をした場合、祖父母も相続放棄が必要?
- 相談例62 (相続放棄)①子供が相続放棄をした場合、孫も相続放棄が必要?
- 相談例61 (相続/不動産登記)⑦登記したいが相続人が認知症です
- 相談例60 (相続/不動産登記)⑥相続登記で税金が免除されるケースは?
- 相談例59 (相続/不動産登記)⑤相続登記で税金が免除されるケースはありますか?
- 相談例58 (相続/不動産登記)④相続ではどんな税金がかかるのですか?
- 相談例57 (相続/不動産登記)③それでも住所が繋がらない相続登記
- 相談例56 (相続/不動産登記)②住所が異なる相続登記
- 相談例55 (相続/不動産登記)①権利証が無くても不動産の名義変更は可能?
- 相談例54 (遺言書/相続)例⑭遺言執行者として何をすれば良いか分かりません
- 相談例53 (遺言書/相続)例⑬同性パートナー(LGBT)の方の遺言
- 相談例52 (遺言書/相続)例⑫パソコンのWordファイルで書かれた遺言
- 相談例51 (遺言書/相続)例⑪鉛筆や消えるボールペンで書かれた遺言
- 相談例50 (遺言書/相続)例⑩チラシの裏に書かれた遺言
- 相談例49 (遺言書/相続)例⑨遺言で貰った不動産を拒否したい
- 相談例48 (遺言書/相続)例⑧余命宣告された方の遺言
- 相談例47 (遺言書/相続)例⑦拇印のみの遺言
- 相談例46 (遺言書/相続)例⑥封筒にのみ捺印の遺言書
- 相談例45 (遺言書/相続)例⑤「相続させない」と記載された遺言
- 相談例44 (遺言書/相続)例④英語で書かれた遺言書
- 相談例43 (遺言書/相続)例③日記の一部に書かれた遺言書
- 相談例42 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例②
- 相談例41 (遺言書/相続)実際にあった遺言書の文例①
- 【遺言書の相談事例】自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリットについてを司法書士が解説!
- 相談例38 【*相続重要判例】子から親への借金に対する消滅時効
- 相談例37 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑧(葬儀費用は誰が払う?)
- 相談例36 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑦
- 相談例35 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑥(課題点3)
- 相談例34 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?⑤(課題点2)
- 相談例33 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?④(課題点1)
- 相談例32 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?③
- 相談例31 なぜ子供のいない方の相続手続きは難しいのか?②
- 【兄弟相続】子供がいない方の相続手続き(子なし相続)の注意点やポイントを司法書士が解説
- 相談例29 相続発生時に配偶者が老人ホームに入居していた場合にも、配偶者居住権は設定できますか?
- 相談例28 配偶者居住権が設定されたら誰が居住建物の固定資産税を払うのですか?
- 相談例27 共有の不動産にも配偶者居住権は設定できますか?
- 相談例26 配偶者居住権を設定した方がいいケースは?
- 相談例25 配偶者居住権を売却することは出来るのでしょうか?
- 相談例24 配偶者居住権を主張するためには、不動産登記が必要ですか?
- 相談例23 配偶者居住権について教えてください
- 相談例22 遺産分割前の預貯金払戻し制度について教えてください
- 相談例21 自筆証書遺言の法務局保管によるメリットは何ですか?
- 相談例20 自筆証書遺言の制度はどのように変わったのですか?
- 相談例19 信託の登記をしようと考えています
- 相談例18 家族信託制度を使う事は何かデメリットなどありますか?
- 相談例17 娘が離婚することになりました
- 相談例16 認知症の父、妹(知的障害)がいます
- 相談例15 「他に相続人がいないことの証明書」の書式ってあるのでしょうか?
- 相談例14 叔父さんの弟が行方不明でどうしていいか分かりません
- 相談例13 25年前に行方不明になった兄がいます
- 相談例12 相続放棄について
- 相談例11 相続の持分を譲渡したいケース
- 相談例10 父親の相続財産をすべて母親に相続させたいケース(1人息子の相続放棄はキケン)
- 相談例9 被相続人が死亡してから3ヶ月経過してしまった相続放棄
- 相談例8 遺産を受け取らないための「相続分の放棄」と「相続放棄」を混同したケース
- 相談例7 相続税の申告が必要なケース
- 相談例6 前妻とのあいだに子供がいる場合の相続②
- 相談例5 前妻とのあいだに子がいる場合の相続
- 【相続】付き合いがない疎遠な親族の相続人になったケースを司法書士が解説!
- 【相続】相続人の1人が海外在住の場合の相続手続きを事例で解説
- 【相続】被相続人が連帯保証人になっていたため相続放棄した事例
- 【相続事例】遠方の金融機関の預貯金の名義を変更した事例を司法書士が解説!
-
相談事例2026/02/19
-
お知らせ2026/02/12
-
相談事例2026/02/04
-
お知らせ2026/01/29
-
相談事例2025/11/24
-
相談事例2025/09/14
-
お知らせ2025/07/22
-
相談事例2025/07/14
-
お知らせ2025/07/08
-
お知らせ2025/07/07